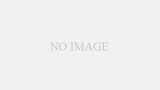操作にストレスを感じる部分はどこか?
操作のストレスは思い通りに動かないことから生まれる
ゲームを遊んでいるとき、一番冷める瞬間は思った通りに動かないときです。たとえばスマホで文字を打つとき、変換が意図と違う言葉になる。あるいは自転車のブレーキが少し遅れて効く。そのわずかなズレがストレスになります。
ゲームにおける操作ストレスも、これと同じです。プレイヤーの頭の中のこう動いてほしいと、実際の挙動が一致しない。このズレが大きいほど、違和感やイライラが積み重なっていきます。
身近な例え話
たとえば自動ドア。歩いて近づいたのに反応が遅れて開かないと、思わず立ち止まってしまいますよね。逆に、自分がドアの前に立った瞬間にスッと開くと、気持ちよく通り抜けられる。このズレの小ささが快適さを生み出しています。
ゲームも同じで、ボタンを押した瞬間にキャラがジャンプすれば気持ちいい。わずかに遅れればなんだかもたついていると感じる。日常生活のドアの開閉の遅れと同じ構造なんです。
典型的なストレス要因を、生活に置き換えてみる
1. レスポンスの遅延
電車の改札でタッチしてもすぐに反応しない。 ほんの1秒でも焦りが大きくなります。
2. 複雑すぎる操作
家電のリモコンにボタンが多すぎて、目的のボタンを探すのに時間がかかる。 シンプルさが大事。
3. 不自然なカメラ
車のバックモニターが逆方向に映っていたらどうでしょう。 見たい場所が見えないと、安全どころか事故の原因になります。
4. 誤操作が起きやすいUI
エレベーターの閉ボタンと開ボタンが小さくて押し間違える。 意図と違う結果が起きると、不満は一気に高まります。
5. 移動のもたつき
スーパーでカートの車輪がガタついて曲がりにくい。 買い物どころか、操作すること自体が苦痛になります。
これらを思い浮かべれば、ゲームの操作ストレスがどんなものか直感的に理解できるはずです。
ストレスが快感に変わるケースもある
ここで重要なのは、ストレスが必ずしも悪ではないということ。ピアノの練習。最初は思うように弾けなくてストレスですが、繰り返して指が動くようになると、むしろ快感に変わります。ゲームも同じで、挑戦のためのストレスはプレイヤーを成長させ、達成感に変わる。
理不尽なストレス、自分の努力ではどうにもならないズレは、ただの不快感でしかありません。開発者に求められるのは、この二つを見極めることです。
操作感を磨くための考え方
1. 日常の不便を思い出す
自分がストレスだと感じた日常の体験を洗い出す。
それをゲームの操作設計から排除する。
2. 最小限で試す
リモコンのようにボタンが多すぎると混乱する。
まずは最低限の操作で成立するかを確認する。
3. 直感に寄せる
自動ドアは近づけば開くという直感に合っているから気持ちいい。
ゲームも押せばすぐ反応する設計を徹底すべき。
4. ストレスを意図的に残す
スポーツに練習があるように、習熟で乗り越えられるストレスは残す。
プレイヤーが上達を感じる余白を作る。
ストレスの少なさはまた遊びたいにつながる
スマホで操作がスムーズなアプリは、つい何度も開きます。逆に重くて反応が悪いアプリは、どんなにデザインが良くても削除してしまう。
ゲームもまったく同じです。グラフィックが豪華でも、操作がストレスなら続きません。逆に操作が気持ちよければ、多少の不満点があっても繰り返したくなる。
まとめ
操作のストレスは意図と結果のズレで生まれる。レスポンスの遅延、複雑すぎる操作、不自然なカメラ、誤操作、移動のもたつき。日常生活のストレスと同じ構造を持っています。残すストレスと消すストレスを見極めること。挑戦を促すストレスは残し、理不尽で快感につながらないストレスは徹底的に排除する。
今日の問い🙋
👉あなたが日常でストレスだと感じていることは何ですか?
その感覚をヒントにすれば、ゲームの操作設計に大きな学びを持ち込めます。日常のストレスをなくす工夫こそが、最高のゲーム操作につながるのかもしれません。